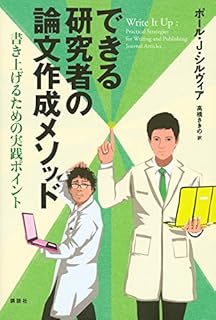<書評します>
1.はじめに
1-1.あの本のレビューを改めて
記事タイトルの本は、今までへ弊ブログの論文の書き方や読み方、執筆のスケジュール管理の記事などで、ちょこちょこと内容を紹介したり、批評したりしてきました。改めて、Twitterで「いいね」が2桁になったら、全体レビューをしようとツイートしましたが、近況報告も兼ねた記事の「学術論文と同人誌を比較して実感したこと - 仲見満月の研究室」で書きましたように、通過した論文改稿の作業が急きょ、入ってきました。そのため、もう一度、自分が論文の書き方を見直すため、きとんと全体のレビューを本記事で行うことに致しました:
できる研究者の論文生産術 どうすれば「たくさん」書けるのか (KS科学一般書)
1-2.本書の目次と全体
上記の本書リンク先から、目次を引用いたします。
-
第1章 はじめに
-
第2章 言い訳は禁物 ――書かないことを正当化しない
-
第3章 動機づけは大切 ――書こうという気持ちを持ち続ける
-
第4章 励ましあうのも大事 ――書くためのサポートグループをつくろう
-
第5章 文体について ――最低限のアドバイス
-
第6章 学術論文を書く ――原則を守れば必ず書ける
-
第7章 本を書く ――知っておきたいこと
-
第8章 おわりに ――まだ書かれていない素敵なことがら
まず、タイトルにある「論文生産術」とありますが、何も学術論文の生産効率アップだけを行う研究者をターゲットにしてはいません。序盤から中盤を読んでいると、しばしば、研究予算の申請書や、助成金の申込書といった研究活動を支える書類の書き方を知りたい人をも、ターゲットにしていることが窺えます。その一方で、あまり、研究発表のパワーポイントの作り方のテクニックや、シンポジウムの報告集に入れる短いレポート文書の書き方は、あまり気を配られておりません。
本書を貫いているキーワードは、一つ。地道にコツコツ書くことであり、一気書きは避けるべきこと。それでは、細かく気になった箇所を確認していきましょう。
2.ポール・J・シルヴィア『できる研究者の論文生産術』をしっかり読む
2-1.序盤(第1~3章)の内容
序盤の序盤の第1章の内容を箇条書きに起こしますと、以下のようになります。
- アメリカの心理学専攻をする者でも、ライティングのスキルは独学の人が多い
- 大学院を出た後、自分で研究プロジェクトを自立して主導できるスキルがないと、研究者をやっていくのは厳しく、そのために、筆者は、各種の研究資金の申請書作成や学術論文といったライティングスキルの水準アップが必須だと考える
- 本書は、研究者にとって必須のライティングスキルの水準アップが目的である
確かに、日本でもアカデミック・ライティングの授業が、学術分野の専門授業と独立したカリキュラムに組み込まれていることが多いです。他の大学院のことは知りませんが、私の行った大学院の文理総合系の部局には、ジャーナル投稿に向けたライティングの授業は設けられてはいませんでした。
筆者の言葉を鵜呑みにすれば、アメリカの大学院でも、なかなか、ジャーナル投稿のためのライティング・スキルの授業はないようです。そのあたりは、第3章の動機付けや、中盤の第4章の仲間づくりと勉強会のところで、スキルアップのコツが紹介されています。
第2章の「言い訳は禁物」のところでは、「とにかく、書かないことを正当化せよ」と、ひたすら、書かないことの言い訳になりそうな事柄が打ち消されています。
- 書く時間がとれない→一週間に数日で一日に2時間ずつでも書く時間を確保せよ
- 先行研究や統計処理に時間をとられる→執筆時間の中に含めて合理化せよ
- 新しいPCとプリンタや、椅子と机が欲しい→今、持っている道具で書け
- 気分がのっている時を待っている→データ上、地道に書くほうが科学的な文書である論文の執筆には適切である、という統計があるので、1の方法で書け
1の執筆時間の確保や管理、やり方については、「論文執筆や研究の作業計画の予定管理法~ちょっとした工夫をしてみる~ - 仲見満月の研究室」の「1.論文執筆や研究の作業計画の予定管理法」で、実際のカレンダー画像を載せています。2については、用意したマンスリーカレンダーに引いた線の日について、2~3時間ずつ、執筆や提出先との連絡メールの時間のやり取りも含めて、スケジュールにぶち込んでしまえば、私は気持ちが楽でした。
3については、「学術論文の書き直し作業の字数を削ること、印刷出力しないと作業が進まない「ぼやき」ほか - 仲見満月の研究室」でも書いたように、印刷した紙原稿に赤入れしてPCで修正→修正データを紙に印刷→赤入れするのループで、推敲作業を進める私には、やはり、ある程度、機動に安定感とスピードのある機械は必要でした。ついでに、私は現在、四肢を痛めているため、ある程度の面積のシートのクッションが付いた椅子と適切な高さの机と椅子がなければ、身体が悪化するらしいです。カフェのカウンター席では椅子が合わず、膝を痛めるので、帰宅してから横になってPCで書いていた時もあります(横になって書くと、首と肩の神経を痛めやすいことも)。
4については、我慢したら不安とイライラで、ストレスになりました。夏休みの宿題の思い出で、計画的に宿題の提出期限までに終えられる人は、4の言い訳は関係ないかもしれません。
第3章の「動機づけは大切 ――書こうという気持ちを持ち続ける」に関しては、技術的なポイントは、1の予定管理の細かいところを書いています。一日につき、決めた数時間のなかで最低限、何ワード書いたか。例えば、エクセルの表に文章を書いた日付と単語数、書いた章や節の名前の項目を作成して、そこに記録して執筆時間を目で見て分かるようにしていく方法が紹介されていました。一種のプロジェクト管理のやり方ですね。つまり、書いた量を「見える化」すると、モチベーションがアップするということです。そうやって、期限までに書類や文章が書けたら、ご褒美にコーヒーを飲んでもいいし、欲しかった物を買ってもいい。ただし、休みはしない。短期の目標をクリア後も、次の期限に向けて書き続けるルーティンは崩さないことが重要だそうです。
2-2.中盤(第4~6章)の内容
第4章は、書き続けるために、互助グループを作って、週一回程度は進捗を発表し合ったり、読書会を開催して知識を高めたり、そういった組織活動のやり方が書かれていました。日本でいうと、自主ゼミや定期的な学生の読書会が近いでしょう。
そうそう、大学教員の読者に向けて筆者が忠告として、学生との勉強会は優先し、また書類チェックも学生との共同グループのものであれば、優先順位を付けるよう、第2章に引き続き、書かれていたかと思います。
第5章は、文章の文体について、記号の使い方から、受動的な文体で書いてはいけないことなどを具体的なアドバイスが書かれていました。本書は、英語の洋書を日本語に訳したものではありますが、受動的な文体で書いてはいけないポイントは、英語と共通するでしょう。昨今の日本のアカデミアでは、特に社会科学系のジャーナルだと、英語の要約や要旨を付けるように義務付けられている点が投稿既定にあると思いますので、英語のアブストやサマリー作成に、この章は役立つでしょう。
そして、第6章が本書の最も重要な箇所になるでしょう。まず、アウトラインの作成をしてから、部分ごとの執筆開始!ということが指摘されていました。このことは、ライター向けの文章書き方の本*1でも、またweb媒体への寄稿する時にも、よく言われるているポイントの模様です。